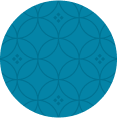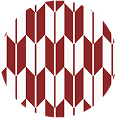スタッフブログ
振袖を着てのトイレの仕方!トイレが難しい理由とトラブルの予防法も
2025/03/18
振袖は成人式や卒業式など特別な日に着る華やかな衣装ですが、トイレに行く際には独特の難しさがあります。
袖や裾の長さ、帯の締め付け、何重にもなる襦袢や裾よけが動作を制限し、トラブルが発生しやすいためです。
当記事では、振袖を着たままトイレに行くときの注意点からトラブルを防ぐ方法、急な生理時の対策まで、安心して1日を過ごすための実用的なアドバイスを紹介します。
普段着と異なる振袖の性質を理解した上で、スムーズにトイレに行けるよう備えておきましょう。
目次
1. 振袖を着てのトイレが難しい理由|予想されるトラブル
1-1. 長さのある「袖」
1-2. タイトで長い「裾」
1-3. 広範囲を締める「帯」
1-4. 幾重にも着る「襦袢・裾よけ」
2. 振袖を着ているときのトイレの仕方
2-1. 【トイレ後】振袖のチェックポイント
1. 振袖を着てのトイレが難しい理由|予想されるトラブル

振袖を着たまま会場内でトイレをするのが難しい原因は、振袖が普段の洋服とは異なる作りであるためです。
しかし、振袖と洋服の違いを理解すれば、トイレに行った際のアクシデントを防ぐことは可能です。
まずは、振袖と洋服の相違点と、それによって想定される洋式トイレでのトラブル事例を説明します。
1-1. 長さのある「袖」
振袖の象徴である長い袖は「振り」と呼ばれ、その長さは1mにも及びます。
普段着ている洋服はもちろん、他の着物と比べても袖が長いのが振袖の特徴です。
洋服は袖がそこまで長くないためトイレ時に持ち上げる必要はなく、袖口が濡れないよう手洗い時に注意する程度です。
しかし、振袖の場合は袖が便器に触れたり、床に引きずったりしないよう気を付ける必要があります。
いつもと同じように過ごすと袖が汚れるだけでなく破れる恐れもあるため、便座に腰掛ける前だけでなく、階段を上り下りする際や腕を前や上に動かす際も、周囲に袖が当たらないよう配慮しなければなりません。
1-2. タイトで長い「裾」
振袖はロングのタイトスカートのように、足の甲に届くほど裾が長く、ぴったりと巻き付けるのも特徴です。
その長さは、草履を脱いだ室内では床からほんのわずかの隙間しか空かないほど。
また、裾がすぼまるように下半身にぐるりと着付けるので足の可動域が限られ、パンツスタイルのように自由に足を動かすのは困難です。
トイレで振袖の裾を持ち上げてから元に戻す際、綺麗に裾を整えられず位置が下がってしまうと、水で濡れている床に裾が付いたり、草履で踏んだりして汚れる恐れがあります。
また、ぴったりと裾が巻き付いているために動きづらく、和式トイレでは用を足すのが難しいと感じられるでしょう。
1-3. 広範囲を締める「帯」
洋服でベルトを締めるのはウエスト部分ですが、振袖の帯は胸下から腰までの広範囲を締めることになります。
ギュッと帯を締め付けられ、息苦しさを感じることもあるでしょう。
特に、腹巻き付きショーツや深履きのショーツなど、ハイウエストタイプの下着を着用すると帯に重なって簡単に脱ぐことができず、無理に引き下げると着崩れする恐れがあります。
また、ボリュームのある華やかな飾り結びにした帯が、便座に深く腰掛けることで押しつぶされることもあります。
帯結びをその場で簡単に直すことはできても、着付け直後の美しい状態に戻すのは難しいでしょう。
1-4. 幾重にも着る「襦袢・裾よけ」
振袖をはじめとする和服は、着物の下に肌襦袢や裾よけ、その下に肌着を身に付けるのが通例です。
肌襦袢とは、着物に汗や皮脂が付かないようにする上半身用の下着を指します。
裾よけは、腰からくるぶしまで長さのある、下半身に巻き付けて使う着物用の下着です。
どちらも着物を心地よく着るのに欠かせない和装用の下着で、振袖を着る際は何枚もの衣服を重ねることになります。
特に、裾よけや振袖の裾は左右から巻き付けて布地を重ねるので、窮屈さを感じやすいでしょう。
トイレ作業の後、肌襦袢や裾よけ、振袖の重ね順を間違えたり、途中で引っかかったりすると裾が綺麗に揃わず、床に付いて汚れる可能性があります。
2. 振袖を着ているときのトイレの仕方

ここでは、振袖が汚れたり着崩れしたりしないトイレの行き方とコツを説明します。
頭で覚えるだけでなく、実際にシミュレーションも行って手順の感覚を掴んでおきましょう。
和装クリップや大きめのハンカチなどのアイテムも前もって用意しておくと便利です。
| 1 | 便座の蓋を閉めて首にハンカチを巻いておく |
| 洋式のトイレの個室に入ったら、振袖の裾が便座の中に入らないよう、まずは蓋を閉めます。また、衿元にファンデーションが付くのを防ぐため、大判のハンカチを三角形にたたみ、首に巻きます。 | |
| 2 | 両方の長い袖をまとめる |
| 着物クリップ(着物用クリップ)もしくは紐の両端に留め具の付いた袂クリップで、袖の袂を帯のところに挟んで留めます。クリップがない場合は、両方の袖を体の前で1つ結びにしましょう。その際、シワを防ぐため強く結びすぎないように注意します。 | |
| 3 | 外側(左側)から順番に裾をめくる |
| 振袖から長襦袢の順番で1枚ずつ裾をめくります。自分から見て左が外側、右が内側になっているので、左手で左側の裾を、右手で右側の裾を持ち、裏返しになるようお尻の上まで1枚ずつめくり上げていきましょう。 | |
| 4 | 肌着で包み込むように裾を持ち上げて固定する |
| 肌着を左と右でそれぞれ分けて持ったら、振袖と長襦袢を包み込むように持ち上げ、肌着の端をクリップで留めます。クリップがない場合は、裾を両脇にしっかりと挟み込みます。 | |
| 5 | 便座に腰掛けて用を足す |
| 便座の蓋を開けてショーツを下ろし、普段よりも便座の前のほうに座ります。深く腰掛けると帯が潰れてしまうので、浅く腰掛けることを意識しましょう。 | |
| 6 | 蓋を閉めて水を流す |
| 用を足したらショーツを上げ、水を流します。水が跳ねて振袖を濡らさないよう、必ず便座の蓋を閉めてから水を流しましょう。 | |
| 7 | 順番に裾を下ろす |
| 裾をクリップから外して両手に持ったら、肌着→長襦袢→振袖の順番で、右から先に下ろしていきます。裾の後ろ側もきちんと元の位置に戻っているか、手で触りながら確認しましょう。 | |
| 8 | 袖を固定したまま手を洗う |
| 袖を下ろすと水に濡れて汚れる可能性があるので、クリップもしくは両脇に固定したままで手を洗いましょう。 | |
2-1. 【トイレ後】振袖のチェックポイント
トイレを済ませた後は、全身鏡などで振袖が着崩れていないかチェックしましょう。簡単な応急処置の方法も併せて紹介します。
| ・裾
裾の後ろ側がめくれたままになっていないか、裾から長襦袢や肌着が見えていないか、鏡で確認します。 ・おはしょり トイレ動作の中でめくれ上がることがあるので、鏡で背面が乱れていないか見ます。おはしょりは、シワのない状態で帯の下側から出ていればOKです。 ・帯 便座に腰掛けた際に、帯が潰れたり歪んだりしていないか確認します。帯の位置が下がっている場合は帯の下に手を入れ、帯の上を持って元の位置に引き上げましょう。 |
3. 成人式当日に生理になりそうorなったときは?
成人式当日と月経日が被ると予想される場合は、ローライズのサニタリーショーツを着用し、生理用品をバッグに入れるようにしましょう。
ハイウエストのサニタリー用ショーツを着用すると、履き口が帯で締められて引き抜けなくなる可能性があるので、振袖を着る際は脱ぎ履きのしやすい浅履きの下着がおすすめです。
万が一成人式当日に生理になった場合は、その旨を着物レンタル店の着付けスタッフに伝えるようにしましょう。
腰回りの補正タオルを調整したり、帯をきつく締め付けないようにしたりするなど、生理中でも快適に過ごせるよう配慮してくれます。
経血の量が多く振袖を汚さないか心配な場合は、タンポンと夜用ナプキンを併用したり、防水仕様のサニタリーペチパンツやペチコートを使用したりすることも検討しましょう。
まとめ
振袖姿でトイレに行くのは、袖や裾、帯、襦袢などで動作が制限されるため、少々難しいと感じることがあります。
振袖でトイレをする際は、袖と裾を持ち上げて汚れを防ぎ、帯が崩れないよう浅く腰掛けるようにしましょう。
トイレ後は、おはしょりや裾などが着崩れていないかをチェックし、整えることが大切です。
急な生理になった場合も、事前の準備や適切な対策を講じておけば、安心して成人式を楽しめます。本番当日までに振袖用のトイレ手順のシミュレーションを重ねておきましょう。
Category カテゴリー
Recently 最新の記事一覧
- 卒業式の袴を安く済ませる方法7つ|レンタル・購入する場合の違いも
- 成人式が雨でも安心!振袖を濡らさないための所作・対策グッズを紹介
- 振袖を着たときの作法とは?動きの基本やマナーを分かりやすく解説
- 振袖の下にヒートテックを着てもいい?選び方や成人式の防寒対策を紹介
- 袴の色はどう組み合わせる?色の印象やおしゃれな組み合わせを解説
- 振袖は寒い?おすすめの防寒対策アイテムを部位ごとに分かりやすく解説
- 2025年振袖人気カラーランキング|Z世代が選んだ色柄TOP10と最新トレンド
- 痩せ型さんに似合う振袖は?体型に合わせた選び方や魅力の引き出し方も
- ぽっちゃりさんに似合う振袖は?おすすめの色・柄・着こなし方を紹介
- 袴のレンタル料金相場|いつから予約を始めるのかも紹介