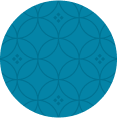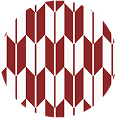スタッフブログ
振袖の柄の種類と意味を古典柄・モダン柄に分けて解説!人気の振袖も紹介
成人式に着る振袖を決める際、お店ではさまざまなタイプの振袖を試着できます。洋服を選ぶときと同じように、振袖にも色や柄・なりたい雰囲気など、多くの要素を踏まえながら見比べることが大切です。ただ、振袖の柄と言ってもどんな柄があるのか知っている方はあまり多くないのではないでしょうか。
ここでは、振袖選びに大切な要素のひとつである「柄」について解説します。
目次
1. 振袖の柄にはどんな種類があるの?

振袖の柄と言っても、どんなものがあるのか分からないことも多いかと思います。振袖の柄には、古くから伝わる意味が込められていたりするものも多いです。ここでは、具体的にどんな柄があり、どんな意味やイメージがあるのかを紹介していきます。
2. 【古典柄】振袖の柄の種類と意味

着物の柄でよく耳にするのが「古典柄」でしょう。成人式というお祝いの場で着用される振袖の柄には、縁起の良いものや願いが込められているものが多くあります。古典柄の振袖は時代に囚われず、普遍的で不動の人気を誇る柄です。
古典柄の中でも吉祥文様(きっしょうもんよう)は、縁起がいい、めでたいという意味を表現した伝統和柄のことを言います。中国の影響を受けたものや、日本で生まれたものなどさまざまです。また柄も、松竹梅や御所車、熨斗、扇、菊、牡丹など複数あります。
以下では、吉祥文様を含めた振袖でよく使われる古典柄を紹介します。
2-2. 御所車(ごしょぐるま)

御所車は、平安時代に貴族が乗っていた牛車を描いた柄です。「高貴さ」「優雅さ」を表し、振袖や婚礼衣装に使うと雅やかな柄行になります。
また、御所車によく似ている柄で、牛車にたくさんの花々を乗せた柄は「花車(はなぐるま)」と呼ばれます。牡丹・菊・桜といったさまざまな花をあしらった花車の柄は、「幸せを招く」意味があるとされています。
2-3. 熨斗(のし)

熨斗とは、もともと鮑(あわび)の身を薄くのして干したものを言います。鮑は長寿を示す縁起物とされており、贈答品に添えられていたようです。現在では、フォーマルな贈り物のシーンで添えられる飾りのことを言います。
振袖の柄としては、「束ね熨斗」として使われていることが多く、おめでたい象徴の熨斗をたくさん束ねていることから、多くの人から祝福を受けていることと、その幸せを周囲の人へも分け合うという意味があります。
2-4. 鞠(まり)

鞠は、手鞠の形を描いた柄です。丸く縁どられた鞠の中には、鞠自体の柄も加えられていて、美しい色彩が女性の魅力を引き立ててくれます。鞠の丸い形から「困難が丸く収まる」や、長い糸で作ることにより「縁を結ぶ」という意味が込められている縁起のよい柄です。
一部の地方では女の子が生まれたときや嫁ぐときに魔除けとして鞠を贈る習慣があり、お守りの意味も持っています。
2-5. 鶴(つる)
鶴は長寿や豊かな生命力を象徴する瑞鳥で、振袖では翼を大きく広げて飛翔する鶴が描かれています。同じく長寿を象徴する亀(かめ)や松(まつ)、めでたい兆しを表す瑞雲(ずいうん)と組み合わせることが多く、躍動感や華やかさを印象づけられる着物に仕上がります。
鶴の柄は「長寿」「子孫繁栄」や「高貴さ」を意味していて、成人式で着用する振袖以外に婚礼衣装など慶事の着物にもよく使われる定番柄です。
2-6. 扇(おうぎ)
扇の柄は扇面を大きく広げた絵で表され、扇の中にも優美な絵柄が描かれます。末広がりの形をしていることから吉兆のモチーフとして使われていて、「繁盛」「開運」などを意味する柄です。
また、扇柄には「地紙(じがみ)」「檜扇(ひおうぎ)」という種類もあります。
地紙は扇に貼る紙のことで、骨のない紙だけの扇型で表される柄です。地紙の中には草花や文様が描かれ、優美なデザインとなります。
もう1つの檜扇は平安貴族が使っていた扇で、木板を綴じた扇面と左右に付いた飾り紐が特徴です。檜扇の柄は優雅さ・格調高さがあり、礼装によく用いられます。
2-7. 桐(きり)
桐は、日本の伝統的な吉祥柄の一つで、高貴な象徴とされる植物です。古くから「鳳凰がとまる木」として尊ばれ、格式の高い家紋や皇室の紋章にも使われてきました。振袖に桐の柄が描かれるのは、幸福や立身出世を願う意味が込められているためです。細やかなデザインで描かれることが多く、上品で洗練された印象を与えます。
2-8. 霞(かすみ)
霞は、ぼんやりと広がる霧や靄(もや)を表した、日本の伝統的な文様の一つです。遠くの風景が霞んで見える様子は幻想的で優雅な印象を与えるため、古くから着物のデザインにも取り入れられてきました。
振袖に描かれる霞模様は、視界を遮ることなく景色をやわらかく包み込むことから、「未来を切り開く」「発展・繁栄」またときには「永遠」を意味するとされています。また、春の季語としても知られ、上品で落ち着いた雰囲気を演出する柄として人気があります。
2-9. 雪輪(ゆきわ)
雪輪は、雪の結晶をくぼみのある円形で表したとされる柄です。
同じ雪をモチーフにした柄には、雪の結晶を精緻にかたどった「雪華(せっか)」があります。雪華と比べると、雪輪は丸みを帯びた優しい形をしている点が特徴です。
雪は春になると水になり、農作物を豊かに育てる源になるため、雪輪柄には「豊作・豊かさをもたらす」という意味があります。成人式の季節感とも合う柄です。
2-10. 貝桶(かいおけ)
貝桶は、「貝合わせ」で使用する貝をしまう容器(貝桶)を描いた柄です。
貝合わせは平安時代から伝わる日本の遊びであり、たくさんの貝の中からもともと対になっていた二枚貝の組み合わせを探します。二枚で一対の貝は形がぴったりと合うため、貝合わせの貝を収めた貝桶柄は「永遠の契り」や「夫婦円満」を意味します。
貝桶は中世で嫁入り道具の1つにもなっていて、女性との縁が深い柄です。
2-11. 組紐(くみひも)
組紐は、細い糸を幾重にも組んで作られた組紐をかたどった柄です。結び目を作った柄がよく使われています。
細く柔らかな曲線を描く組紐は、着物の柄に繊細さや優美さの印象を与えます。檜扇や鞠、貝桶と合わせられることがあり、華やかさの中に曲線の動きやアクセントを加えられる柄です。組紐の柄には「魔除け」「良縁を結ぶ」という意味が込められています。
2-12. 矢羽根(やばね)
矢羽根は、弓矢の矢の羽部分をモチーフにした伝統的な文様で、江戸時代から着物の柄として親しまれています。矢羽根には破魔矢として魔除けの意味が込められ、また「まっすぐ進む」「目標に向かって突き進む」と縁起の良い柄として振袖や袴に使われることが多いです。
矢羽根模様はシャープで力強い印象を与えつつ、すっきりとしたデザインがモダンな雰囲気を演出するため、現代の振袖でも人気の高い柄の一つです。
2-13. 七宝(しっぽう)
七宝は、円が連続してつながる幾何学模様で、「人との縁が広がる」「円満な人生を送る」といった意味が込められています。仏教の七つの宝に由来し、縁起の良い柄として振袖に使われることが多い柄です。輪が重なり合うデザインには「調和」や「繁栄」の願いも込められ、上品で華やかな印象を与えます。シンプルながら洗練された美しさがあり、格式高い古典柄を好む方におすすめです。
2-14. 籠目(かごめ)
籠目は、竹籠の編み目を模した幾何学模様で、古くから魔除けや厄除けの意味を持つ柄として用いられてきました。六角形の連続模様は調和や安定を象徴し、家庭円満や繁栄の願いが込められています。
振袖に取り入れることで、格式のある印象を与えつつ、現代的な洗練された雰囲気を演出できます。伝統的でありながら、シンプルでスタイリッシュなデザインとしても人気の高い模様です。
2-15. 糸巻き(いとまき)
糸巻きは、糸巻きと糸が一緒に描かれていることから「良好な関係を願う」、千切(ちきり)と呼ばれることから「人との仲を固く結ぶ」といった意味があります。長く伸びる糸は長寿や子孫繁栄を表す縁起物です。
糸巻きは繊細で美しいデザインが特徴で、女性らしい優雅さや品格を演出できる点も魅力です。格式のある振袖によく用いられる、縁起の良い模様のひとつです。
2-16. 松皮菱(まつかわびし)
松皮菱は、松の木の皮を模した幾何学的な模様で、大小の菱形が交互に並ぶ特徴があります。力強く美しいデザインで、武家の装束や家紋にも用いられてきた伝統的な文様です。
「松」は長寿や不老長寿の象徴とされており、松皮菱も縁起の良い柄として振袖に取り入れられています。格式ある雰囲気を演出し、大人っぽく落ち着いた印象を与える模様です。
2-17. 雲取り(くもどり)
雲取りは、雲の形を装飾的に表現した模様で、柔らかな曲線が特徴的です。雲は古来より「吉兆の兆し」とされ、天の恵みや神の存在を象徴する縁起の良い柄として知られています。
振袖に描かれる雲取りは、模様全体の区切りとして使われることも多く、華やかさや奥行きを演出します。豪華で格調高い印象を与えるため、成人式や結婚式など格式ある場面にもふさわしい模様です。
2-18. 麻の葉(あさのは)
麻の葉は、正六角形を基にした幾何学模様で、麻の葉の形に似ていることから名づけられました。麻は丈夫でまっすぐに育つことから、「健やかな成長」や「魔除け」の意味が込められており、古くから子どもの着物にも用いられてきた縁起の良い柄です。
振袖では洗練された印象を与え、上品でありながらも力強さを感じさせるデザインとして、多くの場面で用いられています。
2-19. 青海波(せいがいは)
青海波は、扇形を半円状に重ねた波模様で、穏やかな海の波を表現した伝統的な吉祥文様です。無限に広がる波が未来永劫の平和や幸せを象徴しており、「穏やかな暮らしが続きますように」という願いが込められています。
振袖に用いると、優雅で落ち着いた印象を与えつつ、格式ある装いを演出できます。古典柄として人気が高く、幅広い世代に好まれる模様です。
2-20. 流水文様(りゅうすいもんよう)
流水文様は、水の流れを曲線で表現した模様で、古くから親しまれてきた伝統的な文様の一つです。流れる水は「絶え間ない命のつながり」や「清らかさ」「変化」を象徴し、振袖に使うことでしなやかで優雅な印象を与えます。
また、水は厄を流すとされ、縁起の良い意味も含まれているため、晴れの日の装いとしても人気が高い柄です。多くの文様と組み合わせて描かれることも特徴です。
2-21. 亀甲文様(きっこうもんよう)
亀甲文様は、正六角形の幾何学模様を表した柄です。奈良時代の正倉院宝物にも亀甲文様が使われているほど歴史の古い柄であり、振袖姿に格調高さや高貴さを加えられます。名前の通りに亀の甲羅に似ていることも特徴で、亀甲文様は「長寿」の意味がある柄です。
また、亀甲文様柄は上下左右に隙間なく並べられる形であり、複数を連ねると「永遠の繁栄」という意味を持ちます。
2-22. 桜(さくら)
桜は、美しく咲いた桜の花が描かれた柄です。桜は日本の国花であり、春の訪れを感じさせる花として高い人気があります。
桜という名前は「さ」が稲の神様、「くら」が神様の宿る場所を指すという説があり、桜柄は「五穀豊穣」の意味を持つ柄です。
また、さまざまな花が咲く春の中でも、春の盛りを代表する花として「新しい門出」の意味もあります。
2-23. 菊(きく)
菊は、満開の菊花が描かれた柄です。菊は桜と並ぶ日本の国花であり、日本の国章や皇室の御紋などに使われています。古来、菊は邪気を払って長寿をもたらす植物と考えられており、菊柄には「不老長寿」の意味があります。
振袖の柄としては、丸い菊花の「万寿菊(まんじゅぎく)柄」や、長い花びらが乱れ咲く様子を表した「乱菊(らんぎく)柄」が代表的です。
2-24. 牡丹(ぼたん)
牡丹は、咲きこぼれるような花をつけた牡丹を描いた柄です。
中国では牡丹は百花の王と呼ばれていました。日本においても美しい見た目から縁起のよい植物として、古くから着物の柄に使われています。
牡丹柄が持つ意味は「富貴」「繁栄」「幸福」です。牡丹の柄は大ぶりに、色使いも鮮やかに描かれることが多く、着物の柄行に華やかさを演出できます。
2-25. 梅(うめ)
梅は、厳しい寒さの中でいち早く花を咲かせることから「忍耐力」や「希望」、そして「繁栄」を象徴する文様として、振袖にもよく用いられます。
冬から春への季節の移ろいを告げる梅の花は、若々しさや新しい門出を祝う意味を込めて描かれ、成人式や祝いの場にふさわしい柄です。可憐で華やかな印象を与えるため、女性らしさを引き立てるデザインとしても人気があります。
2-26. 藤(ふじ)
藤は、優雅に垂れ下がる花の姿から「優しさ」や「女性らしさ」を象徴する文様で、振袖の柄としても古くから親しまれています。藤はつるを伸ばして成長するため、「長寿」や「子孫繁栄」の願いも込められています。
藤の花房が風に揺れる姿は、しなやかで奥ゆかしい美しさを感じさせることから、成人式や結婚式など、特別な場にふさわしい気品ある柄として人気です。
2-27. 椿(つばき)
椿は、丸みを帯びた花びらと艶のある葉が特徴で、古くから「高貴」や「気品」を象徴する文様として用いられてきました。寒さに強く冬から春にかけて咲くため、「忍耐」や「生命力」といった意味も込められています。
椿は落ちるときに花ごと落ちることから、「潔さ」や「凛とした美しさ」を表すとも言われ、格式ある場面での振袖の柄として選ばれることが多いです。
2-28. 橘(たちばな)
日本に昔から自生している柑橘系の果樹である橘は、古来より「不老長寿」や「繁栄」の象徴として親しまれてきました。
橘は古代の宮中装飾にも使われた由緒あるモチーフで、「高貴さ」や「気品」を感じさせることから、成人式など晴れの日の装いにふさわしい柄として人気があります。縁起の良い文様として、500円玉にも描かれている植物です。
2-29. 紅葉(もみじ)
紅葉は、四季の移ろいを象徴する秋の代表的な植物であり、「長寿」や「世渡り上手」を意味する縁起の良い柄として振袖に用いられます。鮮やかに色づく紅葉は、努力が実を結ぶことや人生の実りを象徴し、未来への希望や飛躍を願う気持ちを込めて描かれます。
秋を象徴する文様ではありますが、桜など他の文様と描かれている着物や振袖の場合は通年で着用することができます。緑色の青もみじの柄は初期に着るのが一般的です。
2-30. 唐草(からくさ)
唐草は、つる草が四方八方に伸びる様子を図案化した文様で、「繁栄」や「長寿」を象徴する縁起の良い柄として振袖に使われます。絶え間なく伸びるつる草の様子から、「家運隆盛」や「子孫繁栄」などの願いが込められており、古くから愛されてきました。
力強くしなやかな曲線は、優雅さと力強さを兼ね備えた印象を与え、振袖に取り入れることで気品ある華やかさが演出されます。
3. 【モダン柄】振袖の柄の種類と意味

「モダン」は「現代的、当世風」などの意味を持ち、「古典」の反対語でもあります。バラや蝶などの洋柄や、リボンやレース、チェック柄など”和”とかけ離れた柄も、総じて「モダン柄」と呼びます。
今風で大胆な着こなしができ、かつ振袖のインパクトだけで個性を演出できます。また、古さと新しさが共存している「レトロモダン柄」も、近年人気が急上昇しています。
以下では、モダン柄の振袖によく使われている柄の種類と意味を紹介します。
3-1. 薔薇(ばら)
薔薇は西洋花で華やかな雰囲気があり、代表的なモダン柄として振袖によく使われています。薔薇と言うと赤色の花が広く知られているものの、モダン柄で使われる薔薇の色は赤色に限りません。
赤い薔薇は「愛」「情熱」、白い薔薇は「純潔」「尊敬」、ピンクの薔薇は「上品」「淑やか」など、色によって柄の意味は異なります。自分が柄に込めたい意味に合わせて色を選ぶとよいでしょう。
3-2. 百合(ゆり)
大きく広がるように咲く百合の花は華やかさがあり、振袖の柄では花を大ぶりに描くなど大胆な構図で使われることがあります。
百合は世界各国で純潔を象徴する花として扱われていて、キリスト教では聖母マリアとの関係性もある花です。百合の柄が持つ意味は「純潔」「無垢」で、特に白い百合は2つの意味を強く表します。色によって意味が異なる場合もあり、黄色は「陽気」「幸福感」、オレンジは「華麗」とされています。
3-3. 蝶(ちょう)
蝶は色彩豊かな羽を持ち、空をひらひらと舞う姿の優美さが好まれ、振袖の柄によく使われています。
蝶は小さな卵から成長し、さなぎを経て、最後は大空へと羽ばたきます。成長とともに変化する姿から、「成長」「立身出世」という意味を持つ柄です。また、蝶の読みは「長(ちょう)」につながり、「不老長寿」という意味も込められています。
4. なりたいイメージ別!振袖のおすすめの柄
前述では振袖の柄についてお伝えしました。しかし柄を知るだけで、成人式に着る振袖を決めるのは少し難しいように感じます。そこでここでは、なりたいイメージにスポットをあて、おすすめの柄や振袖を紹介していきます。
4-1. フェミニン
フェミニンとは、女性らしいことやその仕草のことを言います。やさしく柔らかなイメージで、ファッションでは一般的に、やさしい色合いのスタイルや洋服を指します。
振袖においては、ベージュや流行のくすみカラーのものを選ぶとフェミニンな雰囲気を演出できます。鞠や菊、雪輪などの純粋な古典柄でも、振袖の地色と柄の色のトーンに統一感を出すことでフェミニンさをより表現できます。
4-2. 和モダン
ファッションにおいてモダンとは、都会的でスタイリッシュな姿のことを言います。日本の伝統的な和と現代的なスタイリッシュさを兼ね備えたイメージは、洋服では表現できない、振袖ならではの「和モダン」というイメージで完成されています。
写真の振袖は裾にほどこされた紗綾形の文様と袖の牡丹の花が目を引く、印象深い柄付けです。派手さよりも洗練さを大切にしたい方にとてもおすすめです。
4-3. エレガント
エレガントとは、「優雅な」「上品な」という意味を持つ形容詞です。落ち着いていて、品のいいイメージです。写真の振袖のような、比較的シンプルな振袖は着姿をすっきりと見せ、シックな雰囲気を演出できます。
振袖の柄としては珍しい、写実的に描かれた洋花が大人っぽさを際立たせます。振袖がシンプルなので、帯や小物を合わせたときに互いの良さが引き立ちます。
5. 人気急上昇中!トレンドの振袖の種類
ファッションの流行や、トレンドの移り変わりは移り変わりが速く目まぐるしいものです。洋服と同じように振袖にも流行があるのかというと、そうではありません。厳密に言えば振袖は洋服ほど流行やトレンドの影響を受けません。
毎年新作の振袖は発表されていますが、世の中の流行やトレンドとして反映されているのは主に「色・トーン」です。振袖の柄には流行やトレンドの影響はありません。
以下では、近年登場した目を引く個性的な振袖を紹介していきます。
5-1. レース
総レースの振袖は、華やかで繊細な雰囲気を演出できる振袖です。インパクトもあり、周りと差をつける着姿を求める人にはぴったりです。
一見無地のように見えるレースですが、レース素材が立体感を醸し出しているためシンプル過ぎることなく着こなせます。「全身にレースはちょっと…」という人は、半衿や帯揚などの小物にワンポイントで取り入れるのがおすすめです。
5-2. 無地
無地の振袖は、コーディネートの自由度が高く自分だけの着こなしが叶います。コーディネートによって、古典やモダンなど幅広い装いを楽しめるでしょう。また、シンプルゆえ飽きが来ず、成人式以外でも卒業式や結婚式など様々なシーンで着用できます。
まとめ
振袖の柄は吉祥文様に代表される古典柄や、大胆さや個性を出せるモダン柄など、さまざまな柄があります。柄にはそれぞれ意味があるため、柄に込められた意味を理解して、成人式に合う柄を選ぶとよいでしょう。
振袖の柄選びでは、自分がなりたい着こなしイメージを考えたり、色・トーンのトレンドを押さえたりすることも大切です。気になる柄の振袖があればお店に来店して、積極的に試着をしてみてください。
Category カテゴリー
Recently 最新の記事一覧
- 袴の構造はどうなっている?男女の違いや着付け方・トイレの方法を解説
- 卒業式の袴に合わせるバッグ・カバンは何がいい?種類や選び方を紹介
- 袴には草履とブーツのどっちが合う?それぞれのメリット・デメリット
- 袴と着物の違いとは?主な種類や袴を卒業式で身に着ける理由も解説
- 振袖をレンタルした後の正しい保管方法|失敗しないコツを解説
- 振袖は初詣のとき着ていくのはあり?メリットや注意点・選び方を解説
- 卒業式の袴を安く済ませる方法7つ|レンタル・購入する場合の違いも
- 成人式が雨でも安心!振袖を濡らさないための所作・対策グッズを紹介
- 振袖を着たときの作法とは?動きの基本やマナーを分かりやすく解説
- 振袖の下にヒートテックを着てもいい?選び方や成人式の防寒対策を紹介